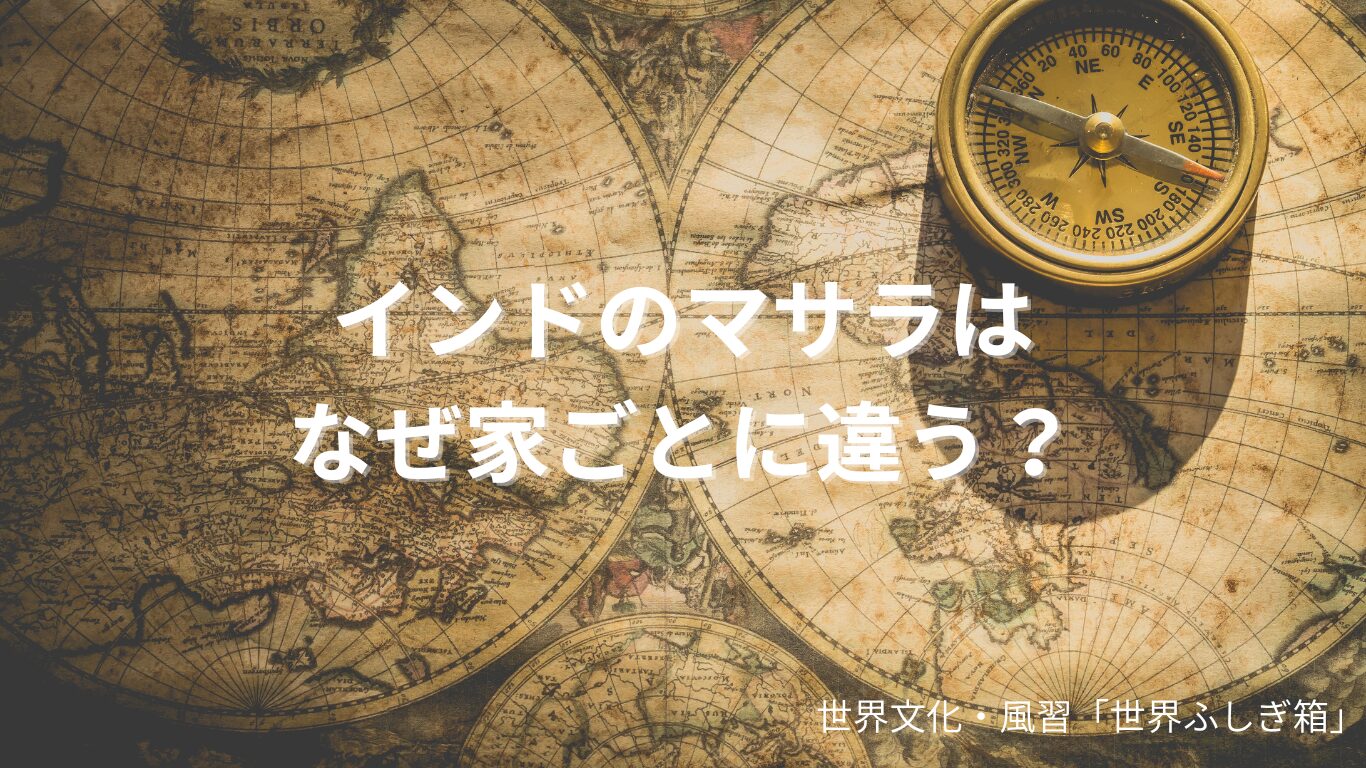インド料理に欠かせない「マサラ」。
日本では“カレー粉”のように思われがちですが、実際のマサラは違います。
- なぜ家庭ごとに味が違う?
- 地域で香りが変わるのはなぜ?
- なぜマサラは“レシピを公開しない家宝”と言われる?
これには、宗教・家族文化・歴史・気候・アーユルヴェーダ が複雑に絡み合っています。
この記事では、インド食文化の中核「マサラ」 を文化人類学の視点で深掘りします。
マサラがインド料理を形作った“歴史的背景”
● マサラの起源は“薬としての調合”だった
マサラ(Masala)は本来、「混ぜ合わせたもの」「調合」 を意味するサンスクリット語系の言葉。
インドでは古代から、
- ターメリック
- クミン
- コリアンダー
- シナモン
- ナツメグ
などのスパイスを組み合わせて薬を作る文化があった。
アーユルヴェーダでは、体質・季節・症状に合わせてスパイスを調合する=治療行為。
この“調合文化”がそのまま料理に転用され、今日のマサラ文化が形成された。
● モグル帝国の宮廷料理が香り文化を発展させた
13〜19世紀にインド北部を支配したモグル帝国は、香り豊かな宮廷料理を発達させた。
- サフラン
- カルダモン
- ローズウォーター
- クローブ
- シナモン
など「香り=権威」とされ、多層的な香りを重ねる技法が進化。
これが ガラムマサラ(芳香系ミックス) のルーツとなった。
● 交易ルートがスパイスの多様性を広げた
インドは古来、アジア・中東・アフリカ・ヨーロッパが交差する交易の中心。
その結果:世界中のスパイスが集まり、調合文化が爆発的に発達した。
マサラの構造(味付け・主食・食材)とその理由
① マサラは“料理によって種類が違う”
インドには多種多様なマサラがある。
代表的なもの:
- ガラムマサラ(芳香系)
- チャートマサラ(酸味の効いた粉)
- サンバルマサラ(南インドの豆スープ用)
- チキンマサラ
- タンドリーマサラ
なぜ料理ごとに違う?
→ 素材の性質に合わせて薬効と風味を変える必要があるため。
例えば肉には温めるスパイス、
豆には消化を助けるスパイス、
魚には臭み消しのスパイスが選ばれる。
マサラは「料理のための薬学」 でもあった。
② 地域によってマサラが変わる理由は“気候差”
北インド:
- 寒暖差が大きい
- 濃厚・油多め・香り強め
→ ガラムマサラが重視される
南インド:
- 熱帯〜高温多湿
- 酸味・辛味を重視
→ クミン・マスタードシード・カレーリーフ
東インド(ベンガル):
- 海と川が多く湿度が高い
→ フェヌグリークやパanch フォロン(5種のミックス)
西インド(グジャラート):
- 乾燥地帯
→ 甘味のあるマサラや保存向きの調合
気候 × 食材 × 水質 × 宗教 がそのままマサラの配合に反映されている。
③ 家庭のマサラが“家の味”になる理由
インドの家庭料理では、マサラの調合を 母から娘へ、娘から孫へ 受け継ぐ。
理由は:
- 家族の体質(消化・暑さ耐性)に合わせる
- 家族の宗教・禁忌に合わせる
- “縁起の良いスパイス”の組み合わせがある
- 健康状態に合わせて微調整する
- 家族が好む香りが決まっている
つまり
マサラ=家族の歴史 × 宗教 × 体質の集大成。
同じカレーでも、家庭が違えば全く違う味になるのはこのため。
マサラに関するマナー・タブー(宗教×文化)
① 調理中の“テンパリング”は神聖な儀式
インドでは油にスパイスを入れて香りを立てる「テンパリング(タルカ)」が重要。
理由:
- 火=浄化の象徴
- 香り=神へ捧げるメッセージ
- 家族の健康を祈る儀式的行為
テンパリングは “料理開始の合図” であり、どの家庭でも静かに行われる。
② スパイスを無駄にするのは大きなタブー
スパイスは古来、金と同価値だったため、無駄にすることは「運気を落とす」と信じられている。
特に:
- こぼしたスパイスを捨てる
- 未使用のスパイスを湿らせる
- 聖なる儀式食のスパイスを粗末に扱う
などは強い禁忌。
③ 食べ合わせには“宗教的禁忌”がある
地域や宗派によっては:
- ジャイナ教:根菜NG
- ヒンドゥー教:牛脂NG、ギーはOK
- イスラム:特定動物油NG
これにより 同じ料理でも宗教によって香りの層が変わる。
他国との比較でわかる“マサラ文化の独自性”
● 日本
→ 調味料(醤油・味噌)が中心
→ インドは調合文化(マサラ)が中心
● タイ
→ フレッシュハーブが主体
→ インドは乾燥スパイス+油抽出の文化
● 中東
→ 香り文化は共通
→ だが薬効・体質に合わせるという思想はインド特有
まとめ
- マサラは“薬”と“料理”が融合したインド独自の調合文化。
- 家庭・地域・宗教・気候によって香りと味が異なる。
- マサラは家族の歴史そのものであり、多様性の象徴。